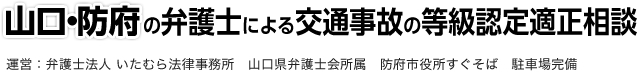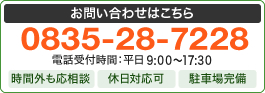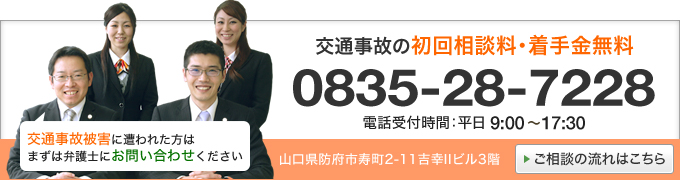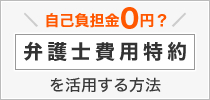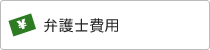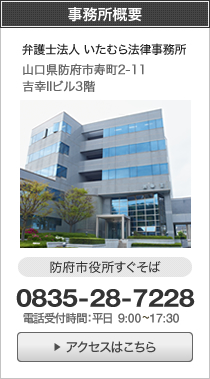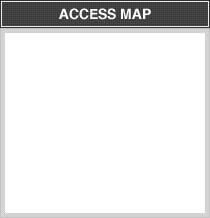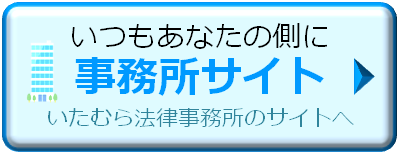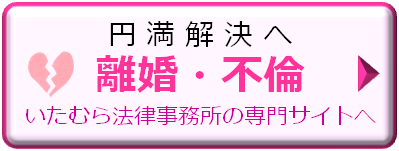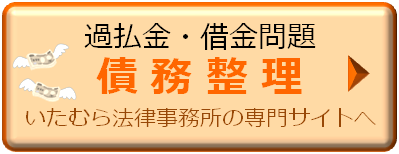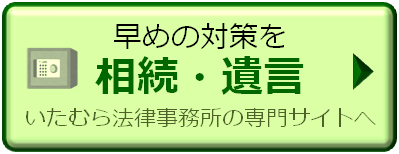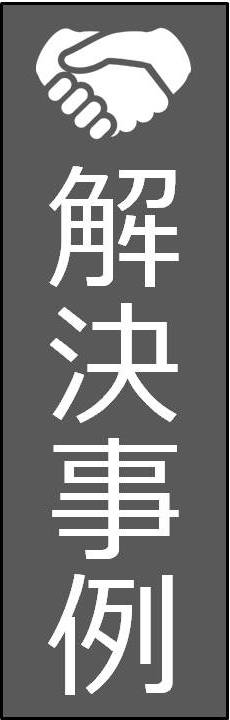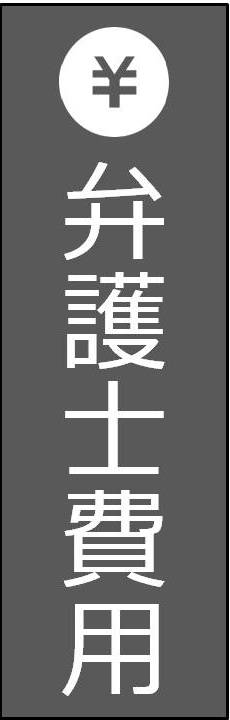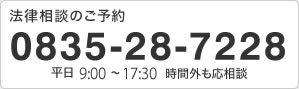高次脳機能障害とは(医学的知識)
神経系統の機能又は精神の障害
 |
神経系統の機能又は精神の障害は,系列としては1つの障害です。
しかし,障害の態様ごとに,①脳の障害,②脊髄の障害,③末梢神経障害,④その他の特徴的障害に分類されます。
|
中枢神経系に分類される脳又は脊髄の損傷による後遺障害は,複雑な症状を呈するとともに身体各部にも様々な障害を残すことが多くあります。
そのため,中枢神経系の損傷による後遺障害が複数認められる場合には,末梢神経による後遺障害も含めて総合的に評価します(頚椎捻挫や腰椎捻挫など)。
他方,脳または脊髄の損傷により生じた後遺障害が単一であって,かつ,当該障害によって後遺障害等級表上該当する等級がある場合(相当等級を含む)には,神経系統の機能または精神の障害の後遺障害等級によることはなく,その等級により後遺障害の認定をすることとなります。
脳の障害・・・器質性障害と非器質性障害
脳の障害は,脳が器質的に損傷したことによる「高次脳機能障害」(器質性の精神障害)及び「身体機能障害」と,脳の器質的損傷が認められない「非器質性の(精神)障害」に分類されます。
脳が器質的に損傷すると,精神機能の障害(記憶障害,認知障害,情動障害など)や身体機能障害(運動障害など)として表れます。
しかし,同様の症状は,非器質性の脳障害によっても出現する可能性があります。
自賠責保険では,精神・神経系統の障害は,それが脳の器質的損傷によるものか否かにより認定される等級が異なります。
そのため,当該症状が脳外傷による脳の器質的損傷部位と整合するか(脳の器質的損傷による症状であるか)否かの認定が非常に重要になります。
器質性障害・・・高次脳機能障害(精神障害)と身体的機能障害(麻痺)
脳の器質性障害については,「高次脳機能障害」(器質性の精神障害)と「身体的機能障害」(神経系統の障害=麻痺)に分類されます。
それぞれに障害が認められる場合でも,併合の方法ではなく,障害の程度及び介護の要否・程度をふまえ,総合的に評価されて等級認定されます。
例えば,高次脳機能障害が5級に相当し,軽度の片麻痺(身体的機能障害)が7級に相当する場合,併合の方法を用いて3級相当とするのではなく,全体病像として,別表第1の1級1号,2級1号,別表第2の3級3号のいずれかに認定することになります。
高次脳機能障害とは
高次脳機能障害は,認知,行為(の計画と正しい手順での遂行),記憶,思考,判断,言語,注意の持続などが障害された状態であると定義されており,全般的な障害として意識障害や認知症も含むとされています。
救命救急医療の進歩により,一命は取り留めたものの,脳が損傷を受けた結果発生するこのような後遺障害が増え続けていると言われています。
「高次脳機能障害」という用語は,医・学術などの専門領域によってそれぞれ定義が異なります。
国は,高次脳機能障害支援モデル事業により集積されたデータ等をもとに,「記憶障害」「注意障害」「遂行機能障害」「社会的行動障害」などを主な要因として,日常生活及び社会生活への適応に困難を有する認知障害について,「行政的見地」から支援を行う対象である「高次脳機能障害」とする「診断基準」が作成しました。
高次脳機能障害の特徴・課題
交通事故による頭部打撲などによって重い意識障害に陥った人が,治療の結果,奇跡的に意識が戻り,歩行や食事ができるようになることがあります。
そのような場合,外見上は完全に回復したように見えます。
しかし,家庭や職場に戻った後,「会話がうまくかみ合わない」,「段取りをつけて物事を行うことができない」,「感情のコントロールができない」などの症状が現れ,様々なトラブル等が発生するため,周囲から「人が変わった」とか「怠け者になった」といった印象を与えることがあります。
高次脳機能障害は,外見から分かりにくい障害ですし,ご本人にも病識が薄い場合が多いです。
また,ご家族や医療・福祉の専門家でさえも,ご本人の症状が脳の器質的損傷の後遺症であることや,対応への理解が十分ではありません。
そのため,障害が見過ごされやすく,ご本人やご家族が周囲から孤立しやすいという特徴があります。
また,日常生活や社会生活に戻って初めて障害に気づいた時には,どこで訓練や支援サ―ビスが受けられるのか分からず,相談もできず,結果として,適正な賠償を受けられないだけでなく,医療や福祉の谷間に落ちてしまうということも,社会的な問題となっています。
死亡事故について、もっと詳しく知りたい方は…
| 死亡事故の損害賠償 | 死亡事故の逸失利益 |
| 事故発生から解決までの流れ | 弁護士紹介 | 事務所紹介 | ||
| ご相談の流れ | 弁護士費用 | 解決事例 | ||
| 交通事故コラム |